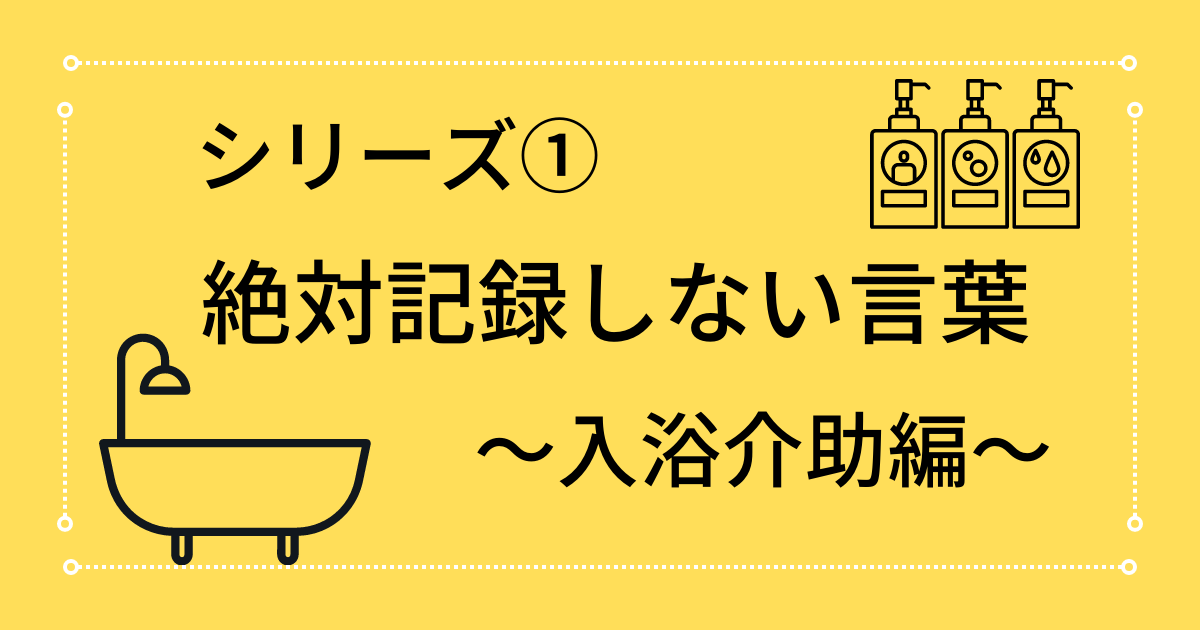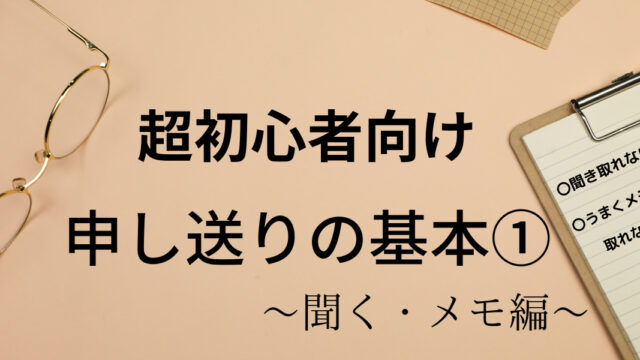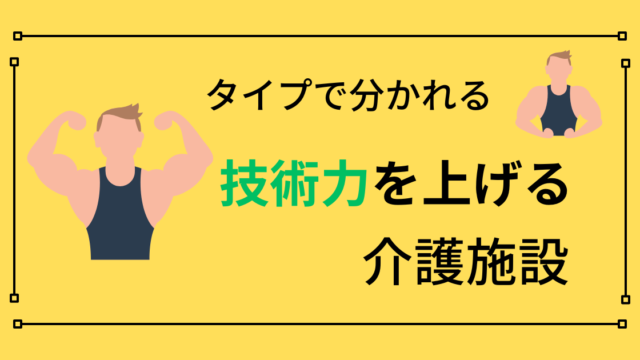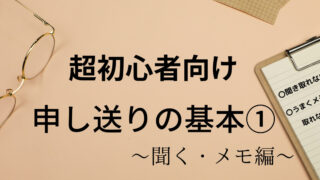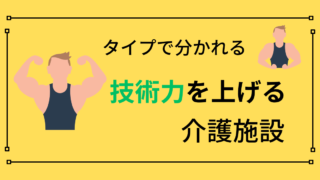「シリーズ①絶対記録で使わない言葉~入浴介助編~」
今回は経験の長い人でも意外と知らない方も多い、絶対に記録では使わない言葉をお話していきます
- 言葉の意味が分かる
- よく使う言葉が分かる
- スムーズに業務ができる
- 業務の分担ができる
入浴介助の流れ
- 入居者の状態確認
- バイタル測定
- 衣類の用意
- 入浴
- 処置
- 服着て、乾かす
- 記録
細かい所は除きますが、以上が入浴介助の流れになります
ユニット型の施設ではこの流れを1名の職員で行いますが、従来型の施設では複数の職員で入浴介助を行います
さらに、ユニット型では1名の職員が①~⑦の流れ全てを担当しますが、従来型では2~3名の職員が関わってきます
そこで、重要になってくるのが職員の連携です
従来型では1日に多くの入居者に入浴してもらうので、職員の連携がとても大事でになってきます
そこで、使うのがこの言葉
「 中 介 」(なかかい)
「 外 介 」(そとかい)
介護現場の記録で使われる言葉
まずは、入浴時によく記録で使う言葉
- 入浴介助を行う
- 〇〇浴を行う
- 入浴介助を行い入浴後に医務から〇〇の処置を受ける
- 誘導時は拒否が強くあったが、入浴後には笑顔が見られた
- 入浴前バイタルにて熱が高くAMの入浴は中止する
記録では上記の言葉を使う事が多いです
内容としては「入浴した/してない」+「その際の様子」を書くことが多くあります
入浴をしっかりとしましたという記録なので、書き方は勤め先の施設に合わせて下さい
介護現場の記録で使われない言葉
ここからは、記録では使われず、職員間でしか話さない言葉になります
- 中介(なかかい)
- 外介(そとかい)
経験が長い方でも施設の経験が少ない方は意外と知らない方もいると思います
以前、勤めていた従来型の施設では入浴介助の度に出てくる言葉でした
何を表すかと言いますと入浴介助中の職員の担当/持ち場です
「中=浴室」「外=脱衣所」と表しています
中 介
中介の担当箇所…浴室の中、洗身、洗髪、湯船がある所です
ここでは次々に来る入居者の洗身、洗髪、を行いながら入浴中である他入居者の見守り、時間管理が主な内容になります
外 介
外介の担当箇所…誘導から、脱衣所まです(浴室以外ほぼ全て)
ここでは、入浴がスムーズに進む様に誘導する入居者の順番を決め誘導したり、医務と連携して処置を行ったり、着脱介助を行ったりと幅広く対応します
担当だけが持ち場じゃない?!
勤務によってその日の持ち場は決まっています
各担当での注意する部分を紹介します
- 1人1人のADLの把握
- 事故(転倒、溺れる)予防
- 時間の管理
- 浴室にいる入居者が全員見える、意識できる様に動く
- 外介との連携
- 時間を意識しての誘導
- 湯冷めしない様に早めの対応
- 衣類を間違えない様にする(古いの、新しいの、本人の、他者の)
- 医務との連携し処置の有無を確認
- 中介との連携
他にも沢山ありますが多くなるので特に注意するものを上げました
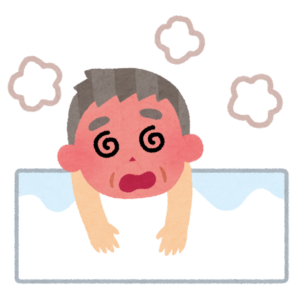
まとめ
中介…浴場の担当
外介…脱衣所担当
読んで頂いた事で実際に現場で言われても動きの予想はついたと思います
施設では1日に多くの入居者が入浴するので、職員も中・外で分かれて業務をしている方が効率的です
効率は良いですがどうしても、作業感が出てしまい私は苦手に感じていました
ここばかりは勤め先の施設によって違いがあってしまいますが、両方経験するとより実感できると思います
そして、中介、外介で重要なのはお互いの連携です
声を掛け合って「〇〇さんそろそろ出ます」「〇〇さん誘導してきます」など声を掛け合える事で次の業務を考えながら仕事ができるのでスムーズに事後とが進みます
大勢の職員、入居者がいるからこそお互いの声掛けを大事にしてみて下さい
おまけ
昔、勤めていた施設では入浴後に足の指の間をドライヤーで乾燥させてから靴下を履いていましたがドライヤーを使う必要はないと記事で見ました
私自身もその1カ所のみで他ではドライヤーを使っている所はありません
ドライヤーを使わずとも、タオルで拭いてから靴下を履くだけでいいですので無駄な業務を入れて疲れない様にお気を付けください